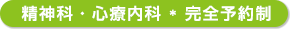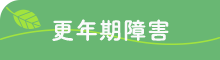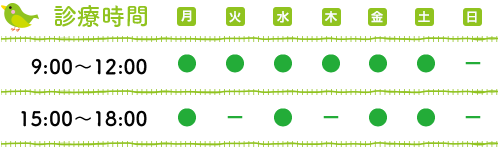心療内科
精神科・診療内科の診療を通して
最大限の「優しさ」で、皆様の毎日を支えます。
- うつ病
- うつ病は主に、精神的および肉体的なストレスや環境の変化、生活習慣の乱れ、さらに脳内の神経伝達物質(セロトニン、ノルアドレナリンなど)のバランスの乱れなど、さまざまな要因が重なって、発病すると考えられています。
- 体がだるくて疲れやすい、食欲がない、眠れない、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないという状態が続いている場合は、うつ病の疑いがあります。
このような症状に心当たりがあるという方は、お早めにご相談ください。うつ病は早期に治療を始めれば、回復もそれだけ早いと言われています。まずは無理をせず、ゆっくり休養をとるようにしてください。
- 躁うつ症
- うつ病だと思っていたら、極端に調子がよく、活発になる時期が見られる場合、双極性障害(躁うつ病)の可能性が考えられます。
双極性障害では、テンションの高い活動的な躁状態と、憂うつで無気力なうつ状態をくりかえします。 - 躁の症状が軽い場合は、最近調子がよいと感じるだけで、躁症状の自覚が乏しく、うつ症状だけ自覚されるため、うつ病と認識されている場合もあります。
双極性障害は「躁」「うつ」の波をいかにコントロールするかが治療目標です。
- 心身症
- 様々な要因によって引き起こされる心理社会的ストレスが体におよぼす病気の代表的なものが心身症です。
心身症というと、こころの病気と思われがちですが、ストレスの蓄積によって、身体に疾患が発症した状態をいいます。
特定の部位のみでなく、循環器系、呼吸器系、消化器系、神経系、泌尿器系などと、あらゆる疾患につながります。
- 統合失調症
- 通常10~30代に発症する病気で、幻覚や妄想という症状が特徴的な精神疾患です。
初期の症状は、不機嫌、親への反抗、成績の低下、昼夜逆の生活、友人との交流が少なくなるなど、反抗期の状態に近い状態に陥る場合もあります。
これが「誰かに見られている」「尾行されている」など、奇異な内容を含むようになったり、全く話さなくなったり、興奮状態になったりするなど多彩な症状が現れるのが統合失調症です。特長のひとつとして、本人は病気、あるいは異常であるのではないかと思っていないことが見られます。
ストレスにより再発しやすいため、うまく付き合っていく方法をご家族も含め一緒に考えていくことも重要です。
- 社交不安障害
- 社交不安障害(SAD:Social Anxiety Disorder)は、人前で話したり、食べたり、初対面の人に挨拶するのが恥ずかしいなど、ある特定の状況や、人目を浴びる行動への不安や他人に悪い評価を受けることに強い苦痛を感じ、汗をかいたり、赤面したり、震えたり、口が渇いたりするなどの身体症状が現れる病気です。
- このような状況を避けようとして学校や仕事に行けないなど、引きこもりがちになったり、社会生活や日常生活に支障が出たり、人間関係がうまくいかなくなる場合がありまとす。
社会不安障害は放っておくと、うつ病などになることもあるので、上記のような症状がみられる場合、一度ご相談ください。
- 不安障害
- 精神疾患の中で「不安を主症状とする」疾患群を不安障害といいます。その中には、特徴的な不安症状を呈するものや、原因がトラウマ体験によるもの、体の病気や物質によるものなど、様々なものが含まれています。中でもパニック障害は「不安」が典型的な形で現れている点では、不安障害を代表する疾患といえます。
- 主な不安障害
- パニック障害
- 強迫性障害
- 外傷後ストレス障害
- 急性ストレス障害…など
- パニック障害
- 体の病気ではないのに、突然、動悸、呼吸困難感、発汗のような身体症状が突然あらわれ、この症状が何度も起こると、過度に心配となって外出などが極端に制限されてしまう病気です。原因は様々ですので、パニック発作の頻度と程度を減少させ、病的状態を緩和し、行動の制限等の患者さんの社会的な機能障害を改善することが必要です。
- 不眠症
- あまりよく眠れない、寝ようと思っても眠れない…
- 眠りたくても眠れない不眠症や、時と場所を選ばずに強い眠気に襲われる「睡眠異常」などの睡眠障害。
不眠症をはじめ、日本人の4人に1人は眠りに関する問題を抱えていると言われています。
どの症状も放置すると不眠からくる倦怠感や、日中耐え難い眠気が出て仕事や生活に支障をきたしてしまう場合も少なくありません。集中力や注意力の低下を招き、精神的、肉体的疲労をよりひどくしてしまうため、早めの対処が必要です。 - 適応障害
- ある特定の状況や出来事が、とてもつらく耐えがたく感じられ、そのために気分や行動面に症状が現れます。たとえば憂うつな気分や不安感が強くなるため、涙もろくなったり、過剰に心配したり、神経が過敏になることもあり、無断欠席や無謀な運転、喧嘩、物を壊すなどの行動面の症状がみられることもあります。
- ストレスとなる状況や出来事がはっきりしているので、その原因からを取り除けば、症状は次第に改善します。しかしストレス因から離れられない、取り除けない状況では、症状が慢性化することもありますので、その場合はカウンセリングなどで、ストレスに適応する力をつけることも、有効な治療法です。
- 自律神経失調症
- めまい、肩こり、頭痛、頭が重い、手足のしびれや痛み、手足が冷える、顔がほてる、動悸 、下痢、便秘、胃がおかしい、眠れない…。
- 日常よく起こりがちな症状は、いろいろ検査をしてもこれといった原因が見つからなかったり、自分が考えているよりも病気の程度がずっと軽く、検査結果からは症状の重さを説明できない場合があります。
このような場合、自律神経失調症の可能性があります。 -
自律神経は、その時々のからだの状況に応じて、意思とは無関係に自動的に働き、体内をつねにベストの状態に保ち続ける神経です。自律神経のバランスが乱れると、前述のような症状がいくつもの症状がかわるがわる現れたり、同時に発症することもあります。
検査結果などから、周囲からは「たいした事ない」と見られ、その無理解な態度にさらに苦しい思いをすることもあり、自律神経失調症は検査結果だけで語ることができない病気だということを正しく理解することが必要です。 - 認知症
- 加齢による脳の老化とは別に、誰もがかかる可能性のある、身近な病気のひとつです。
認知症とは、後天的な脳の器質的障害により、いったん発達した脳の機能が低下した状態をいいます。
記憶障害や見当識障害、理解や判断力の低下など、社会生活や日常生活に支障をきたし、場合によっては治療や介護が必要となります。 - 認知症は『生活に支障をきたすような認知機能障害が現れた場合』 に認知症と診断され、原因によっては症状が急激に進んだりする場合がありますので、早期発見、早期治療で進行を抑え、症状を軽くすることが大切です。
- 更年期障害
- 女性ホルモンのひとつ「エストロゲン」が、閉経や加齢により、卵巣機能が低下するに従って徐々に減っていくため、この変化に体がついていけずに起こるのが「更年期障害」です。最近では女性だけでなく男性も、加齢に伴う男性ホルモン(テストステロン)の低下によって引き起こされるLOH症候群(加齢男性性腺機能低下症候群)も見られます。
- 症状は個人差があり、不調をほとんど感じない人もいれば、ホットフラッシュ(顔ののぼせ、ほてり)、発汗などをはじめとして、日常生活に支障をきたす重い症状の人もいます。更年期障害かな?と感じたら一度ご相談ください。
当院ではマイナンバーカードや健康保険証によるオンライン資格確認
(保険資格の確認、薬剤情報・特定健診情報の取得)を行っています。
ご来院の際は保険証利用登録済みのマイナンバーカード、あるいは健康保険証をお持ちください。
当院でのお支払いは現金のみとなっております。